いつもお世話になっている蕎麦研さんが、スローフードに挑戦と始めたそばの栽培。
キウイフルーツカントリーの平野さんに畑を借りて、その畑を耕し、ソバの実を蒔いて、蕎麦を収穫と進んで、今日は蕎麦の脱穀作業。
これまでソバの実を蒔くのを少し手伝っただけなのだが、久しぶりに予定が会って、お手伝い。
蕎麦、脱穀会場のハウス内には収穫されて乾燥された蕎麦が並ぶ。
格好な量があるような気がするのだが、はたして今日だけで全部脱穀できるのか?
米の脱穀さえも見たことはあっても、ソバの脱穀というのは見るのもやるのも初めて。
米の脱穀については叩いて脱穀から、千歯扱き、脱穀機 と進化しているのだが、ネット上を見てもソバの脱穀の方法というのは意外と定番の方法が見つからなかったりする。
から竿とかマドリと言われる物で叩いて脱穀する方法、それから見かけてなるほど思ったのが新ソバ脱穀①(動画あり) – 百姓の田舎暮らし – Yahoo!ブログと言った方法。
コメのように比較的長さがそろっていて、しかも先の方にだけ実があるのと違って、ソバの実というのはこんなふうに実のある場所が違ったりする。
叩いてみたりもしてみたのだが、なかなか実が取れてくれない。
結局の処、少しずつ手に取り、手でしごいて脱穀すっるのが、今回はしっかり脱穀できて良い方法だった。
ソバを手でこいで脱穀し、ふるいに掛けて大きめの枝を分離して、とりあえず袋の中に。
収穫したソバの脱穀が済んだのは、お昼も廻ってしばらく経ってから。
その後出てきたのが唐簑(とうみと)言う、木製の手回し式の送風機。
自分が幼い頃には、すでに使われていなかったようだが家の裏の方にもあってハンドルを回して遊んだ覚えがあるのだが、小型とはいえまだ手回しの唐簑があったのはビックリ。
でも、これで大助かり。
唐簑という機械、上から脱穀したソバを入れ、手前のハンドルを回して起きる風に当てることによって、軽いゴミは出口から出て行き、比較的重いソバの実は下に落ちることから、ゴミと実を選別できる。
多少の枝と、それから石や、ソバ以外の実は一緒になってしまうのだが、大半の枝等があっという間に選別できる。
原理としては知っていたのだが、実際に使ってみると、これがなかなか優れもの。
先人の知恵という物は、素直にすごい。
未だに、原理としては同じ方法で選別されていたりする。
で、収穫されたソバの実は、こんな感じ。
これまたレトロな秤で、一袋ずつ計って総重量を計算。
その計算に、W-ZERO3の Excel Mobile を使ったりというのが、ちとミスマッチだったりしたのだが。
総重量としては家の末息子のちびのほぼ1.5倍程度。
多いのか少ないのかは分からないが、まあ、最初としてちゃんと収穫できただけでもOK、では(^^ゞ
とりあえず脱穀、選別作業が終わるこりには、日もずいぶん傾いて、色づいてきた里山に夕日の赤がまた良し。
お疲れ様と出していただいた、あったか汁粉が、またありがたい。
蕎麦の脱穀
 「深」のめも
「深」のめも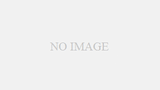
コメント
土曜日はお疲れ様でした。
今回は「深」さんご一家の大活躍により、無事に脱穀が終わりましたね。
娘さんにまでご登場いただいて、ありがとうございました。
うちの娘だったら、絶対に来てくれませんけどね。(ちょっとだけうらやましいです)
今回の蕎麦の脱穀のレポートは、いつになく力が入っていますねぇ。
詳細なレポートありがとうございます。
参加できなかったけど、当日の様子がよくわかりました。
次はいよいよ、製粉&新蕎麦会ですね。楽しみです。
>T川さん
こちらこそ家族4人、なかなか体験できないような良い体験をさせていただきました。
私も娘がついてくるとは思っていなかったのですがね(^^ゞ
レポート、実は当日の前に、ネットでソバの脱穀の方法を調べていたのですが、なかなか見つけられず、もしかしたらそういった人が大勢いるかもと思って、微力ながら詳しく書いてみました。
まあ、どれだけ役に立つかは分かりませんが(^^ゞ
新蕎麦会も参加の予定です。
おいしい蕎麦を楽しみにしています。